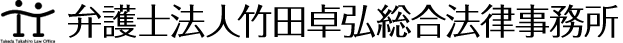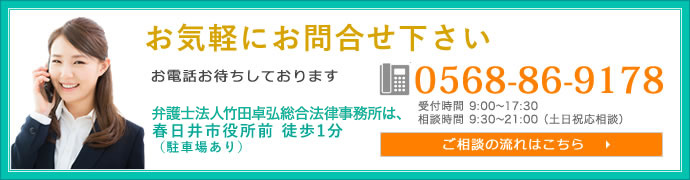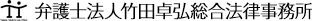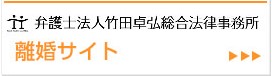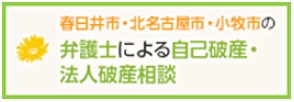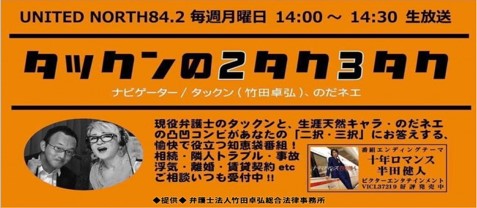遺留分とは・特別受益
遺留分とは、「一定の範囲内の相続人が最低限保障されている相続分」のことです。自分の財産は遺言に よって「誰にどのように引き継がせるか」を自分の意思どおり決めることができます。法定相続人の中の特定の人(財産を引き継いでほしい子や配偶者)や、法 定相続人以外の第三者に全財産を遺贈することも可能です。しかし、その結果、本来相続できるはずの遺族が全く財産をもらえず生活に困ってしまうということ もあります。
遺言によって遺言者の意思は最大限尊重されますが、一方で残される家族の生活も保障されているのです。
遺留分の権利があるのは誰か
遺留分の権利を持つ人を遺留分権者といいます。誰でも遺留分を有する訳ではありません。
遺留分を有する相続人は、配偶者、子(代襲相続人を含む)、及び、父母などの直系尊属のみです。兄弟姉妹は相続人となっても遺留分はありません。遺留分の割合は誰が相続人になるかによって異なります。
■遺留分の割合
| 相続人の範囲 | 遺留分の割合 |
|---|---|
| 直系尊属(父母、祖父母)のみの場合 | 1/3まで |
| 配偶者のみの場合 | 1/2まで |
| 子供のみの場合 | 1/2まで |
| 配偶者と子供の場合 | 1/2まで(配偶者1/4、子供1/4) |
| 配偶者と直系尊属の場合 | 1/2まで(配偶者1/3、直系尊属1/6) |
| 配偶者と兄弟姉妹の場合 | 1/2まで(配偶者1/2、兄弟姉妹なし) |
| 兄弟姉妹のみの場合 | 遺留分の保障なし |
例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合、被相続人が8,000万円の遺産全額を、慈善団体に贈るという遺言をしていた場合、その1/2の4,000万円は遺留分となり、配偶者と子供2人で、この2,000万円を配分することになります。
相続分の指定、遺贈、贈与によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、自己の遺留分を請求することができます。これを「遺留分減殺請求」といいます。
特別受益とは
相続人間での不公平をなくすために設けられた制度で、具体的には、相続人に対して死亡の何年前であろうと遺贈及び一定の生前贈与といった財産が認められた場合、その贈与した財産を含めて相続財産とし、遺産分割を行います。
特別受益の対象となる財産
・遺贈されたもの
・婚姻や養子縁組のために贈与されたもの(結納金・支度金・持参金・新居等)
・生計の資本としての贈与(開業資金・住宅購入資金・高額な学費等)
・生命保険金 ※特段の事情がある場合に認められます
(保険金は遺産ではなく、保険金受取人(相続人)の固有財産※死亡退職金は裁判例において争いがあります)
寄与分とは
相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がある場合に、他の相続人との間の実質的な公平を図るために、その増加をさせた相続人に対して、相続分以上の財産を取得させる制度のことです。
寄与分の対象となること
・親の家業に従事して親の財産を増やした
・寝たきり状態の親を自宅で介護をして親の財産の減少を防いだ
寄与分が認められる人
・共同相続人
・代襲相続人
・養子
・相続人の配偶者
代表弁護士 竹田卓弘
最新記事 by 代表弁護士 竹田卓弘 (全て見る)
- 春日井市教育研究所が発行している、研究所だより「春風」に竹田弁護士の寄稿が掲載されました - 2022年9月15日
- 夏季休業のお知らせ(2022年) - 2022年6月19日
- 夏季休業のお知らせ - 2021年8月12日